起業家支援プログラム(エントリーコース)
GTIE GAPファンド エントリーコース 第3回 2025 2nd 採択チーム一覧
エントリーコースは、起業を目指すGTIEに参画する大学に所属する研究者等を支援する、初めのステップとなるGAPファンドです。
公募内容はこちら
生理的な弁輪運動を実現する3D構造外植型大動脈弁輪リングの開発
大動脈弁閉鎖不全症は、心臓の拡張期に大動脈弁逆流が生じる疾患であり、日本では年間約5000例おり、活動性の高い50歳代に多い。弁尖を温存する大動脈弁形成術は、弁置換術と比較して生命予後が有意に良好であると報告されているが、日本では弁置換が約93%、弁形成が約7%であり、弁形成術は普及していない。その要因として、弁形成術には高度な手技が求められ、優れた弁形成用リングが存在せず、術式が標準化されていないこと等が挙げられる。本研究では、(1) 三次元形態の再現性、(2) 大動脈基部外側から形態を矯正、(3) 適度な硬度による弁輪運動形態の維持、(4) 術式の標準化を可能とする構造設計といった特徴を備えた、新規大動脈弁輪形成リングを試作・開発する。加えて、実用化に向けて、知財ポートフォリオを検討し、事業化に向けたアライアンスについても検討する。

サルコペニア予防のための筋量・筋質イメージング・ウェアの事業化
高齢化が進行する日本社会において、加齢に伴って筋量および筋質が低下するサルコペニアは、深刻な社会問題となりつつある。サルコペニアの予防には、早期の発見と介入が重要であり、そのためには筋量だけでなく筋質の評価も必要不可欠である。しかし、従来のモダリティでは筋質の正確な評価は困難である。
そこで、非侵襲的な可視化技術である電気インピーダンストモグラフィ(EIT)法を用いた、筋量・筋質イメージング・ウェアを開発している。本製品は、多数の生体電極を内蔵したウェアラブルセンサーと小型の外部ハードウェアを組み合わせたものであり、筋量・筋質の状態や、運動・リハビリ時における筋区画ごとの変化を、リアルタイムで4D(3次元空間+時間)画像としてスマートフォン上に表示することが可能である。
本技術を医療現場および地域社会に実装することで、サルコペニアの予防および継続的なモニタリングの実現を目指す。

企業の不正会計検知AIモデル開発とその社会実装
近年、日本では粉飾決算などのコンプライアンス違反企業の倒産が増加しており、その背景には市場からの圧力、事業構造の複雑化、手口の巧妙化があると考えられる。こうした倒産リスクを未然に防ぐため、金融機関は多大なコストをかけて審査を行っているが不正会計を見抜くには実務経験に加え、新たな不正会計を予見するための研鑽が日々必要であり、実務家が十分なスキルを習得するには長期間と多大な費用を要する。本プロジェクトは、高精度AIによる不正会計検出手法の社会実装を目指し、金融機関のみならず、投資会社・証券会社・一般事業会社・監査法人など多様な顧客を対象とする。本技術は、不正の有無だけでなく、不正の理由や利益調整の有無まで明らかにすることを目指している。また、財務諸表のみを入力すれば判別できるソフトウェアを開発することで、顧客の検知に伴う労力を最小限に抑え、幅広い適用を可能とする。
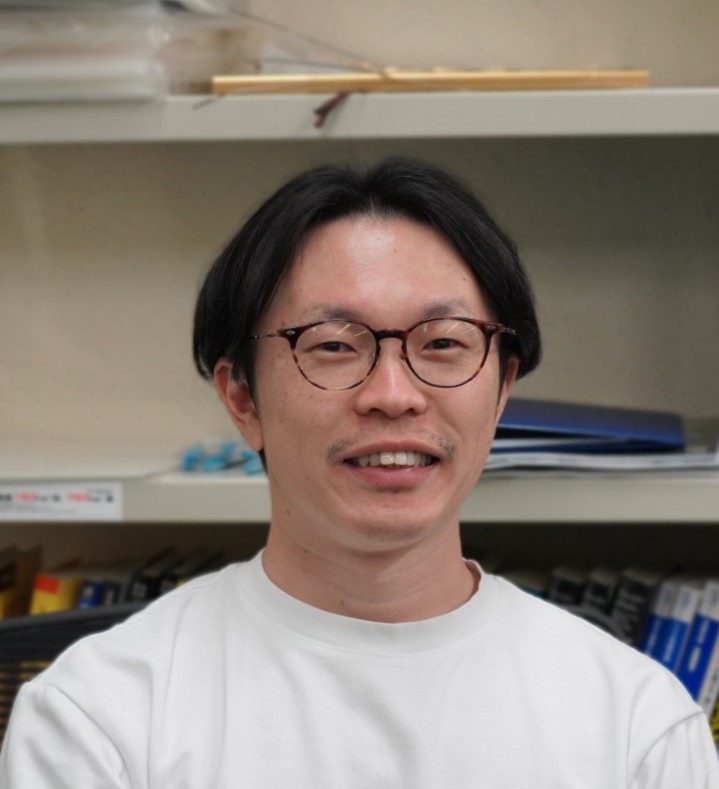
イベントカメラと計算撮像の融合による光沢・透明物外観検査の実用化
本課題では、輝度変化の検出に特化した特殊カメラである「イベントカメラ」と、光学的な情報符号化と計算機による復号によって情報を撮像する「計算撮像」を融合することで、従来の画像検査では対応困難であった光沢・透明物を対象とし、高速かつ省計算・省電力で外観検査を実現する。光沢や透明物の製造現場では、熟練した目視検査員が不可欠であるというボトルネックを解決し、工程の削減および自動化という価値提供を目指す。対象市場である製造業、特に自動車産業への深いヒアリング調査を通して、検査対象物ごとの具体的な市場規模を明確にする。また、実際の不良サンプルを用いた検証により、開発項目要素の明確にし、顧客導入に向けた検査システムの設計仕様を明らかにする。

「隠れ炎症」可視化技術2SCを活用した次世代型動脈硬化予防薬の開発
日本では平均寿命と健康寿命の差が約12年あり、寝たきり高齢者の増加が深刻な社会課題となっている。主因は心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化性疾患であるが、これまでLDLの酸化を防ぐ抗酸化剤による予防が試みられてきたものの、臨床的な有効性は確認されておらず、実用化には至っていない。またコレステロール(スタチン製剤)、血圧、血糖を下げる対症療法薬があるが、依然として心疾患の患者数は増加している。
代表者は、酸化とは異なる発症経路に着目し、ミトコンドリア異常から生じる翻訳後修飾「2SC」を動脈硬化マーカーとして世界で初めて特定・特許化している。これにより、これまで見えなかったリスクを血液検査で可視化し、診断と薬効評価が可能となる。今後は2SC測定系の提供と、抗炎症作用を有する革新的動脈硬化予防薬の開発・上市を目指すスタートアップを設立し、年間10兆円を超える市場の創出を狙う。

野田 拓実
Takumi Nodaフレキシブルプローブによるハンズフリーな超音波イメージングの実現
従来の超音波診断装置では、医療者がプローブを手で持ち観察部位に押し当てる必要があるため、診断中に片手が占有され他の手技との両立が難しいことや、長時間の連続モニタリングが困難であるといった課題があった。そこで我々はこれまでに、皮膚に柔軟に貼り付け可能な布製フレキシブル超音波プローブと、プローブの変形を推定して正確な画像を再構成するアルゴリズムを開発してきた。これらを組み合わせることでハンズフリーでの超音波撮像が可能となり、上記の課題を解決できる。本研究開発では、フレキシブルプローブによる超音波計測を制御するポータブル装置を新たに開発し、臨床現場における本技術の有用性検証を可能にする。また、医療従事者へのヒアリングを行い、製品に求められる要求仕様を明確化する。
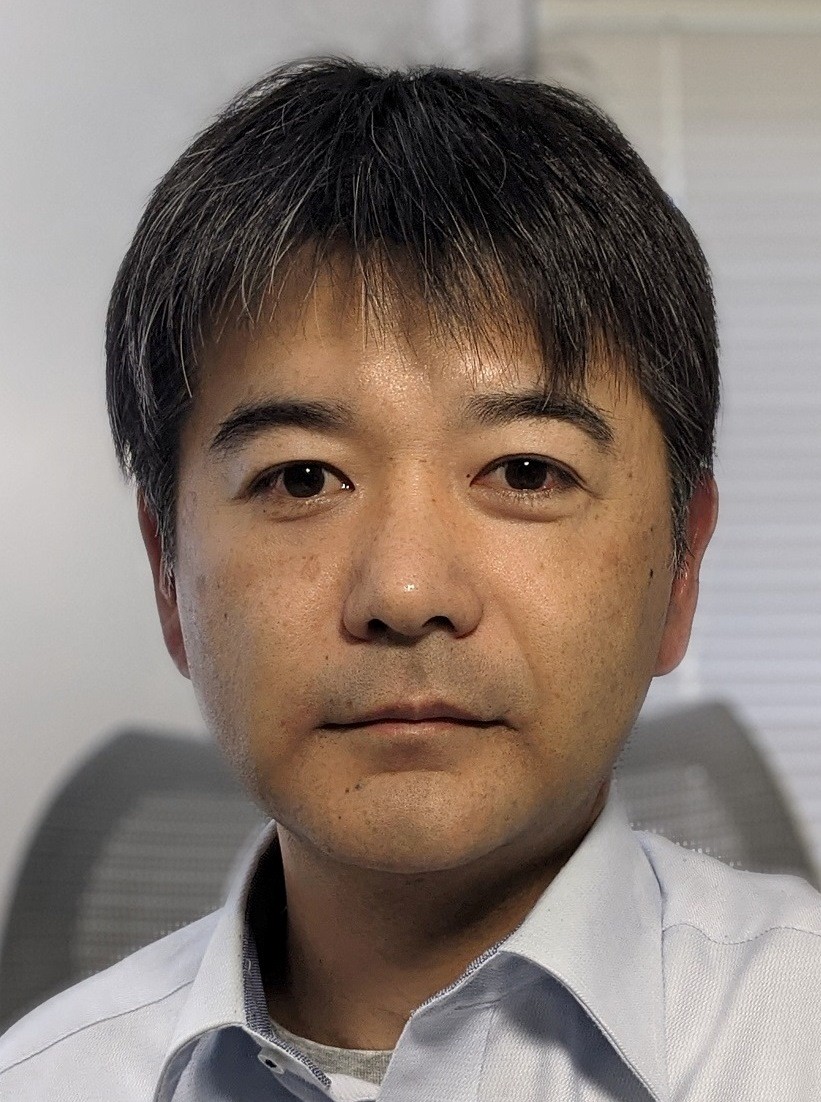
ヒト毛乳頭細胞の産生する細胞外小胞による男性型脱毛症治療
本事業の対象疾患は脱毛症である。全世界に膨大な数の脱毛症患者が存在する。本事業では、細胞外小胞およびmicroRNAを用いて、男性型脱毛症の革新的な治療薬の研究開発に取り組む。細胞外小胞は、細胞間のコミュニケーションに利用されていることから、細胞の種類や周囲の微小環境によって含まれる情報(機能分子)が異なる。本事業では、独自の培養環境下においてヒト毛乳頭細胞から産生される細胞外小胞そのものを利用した治療法、およびそこに含まれるmicroRNAを解析して機能主体であるmicroRNAを利用する治療法を確立し、男性型脱毛症治療に適した治療薬を提供する。

直感的にロボットや車両等を操縦できるコントローラ
直感的な遠隔操作ロボット用コントローラIFHDの技術を活用して、市販用のデバイスを開発し、事業化することで誰でも直感的に多様なロボットや乗り物を操作できる社会を実現するスタートアップ企業の設立を目指す。本コントローラは、立体的かつ多自由度な速度制御を要するものであれば、ロボットアームやショベルカーなどの重機、内視鏡、ドローンといった幅広いアプリケーションに適用可能である。本コントローラを用いれば、誰もが簡単かつ正確にロボットや車両等を操作できるようになるため、人手不足の解消や操作事故の軽減、更に高度なタスクの達成などが可能になる。本コントローラは構造面および制御面の双方において独自のモデルや工夫を施しているため、デバイス単体かつ制御ソフトウェアの販売を予定している。
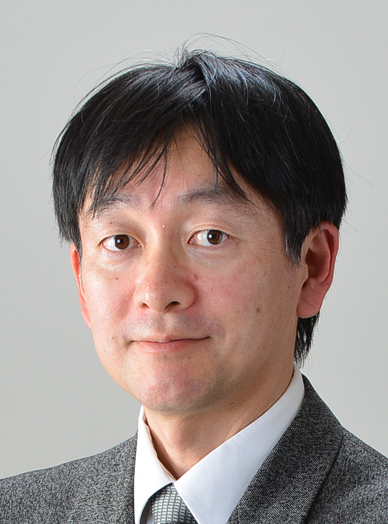
脳卒中患者の歩行練習支援技術に関する研究開発
VRにおける歩行感覚提示装置の技術を活用した脳卒中患者向け歩行リハビリテーションシステムGait Masterを開発する。本プロジェクトでは、より良いリハビリを提供するために「広範な患者に効果があり、医療従事者の負担を軽減し、受容可能な価格のリハビリ機器」のコンセプトで、有効性、運用性、経済性を両立した機器の実現を目指す。また、ステークホルダーである患者、理学療法士、医師、病院経営者にとって本システムを導入するメリットを明確にし、製品仕様に盛り込むことでより普及しやすい環境を作り出す。起業に際しては主な顧客を急性期および回復期のリハビリテーション病院に定め、より迅速な普及のために同領域に強みを持つ企業へ会社売却することをゴールとする。
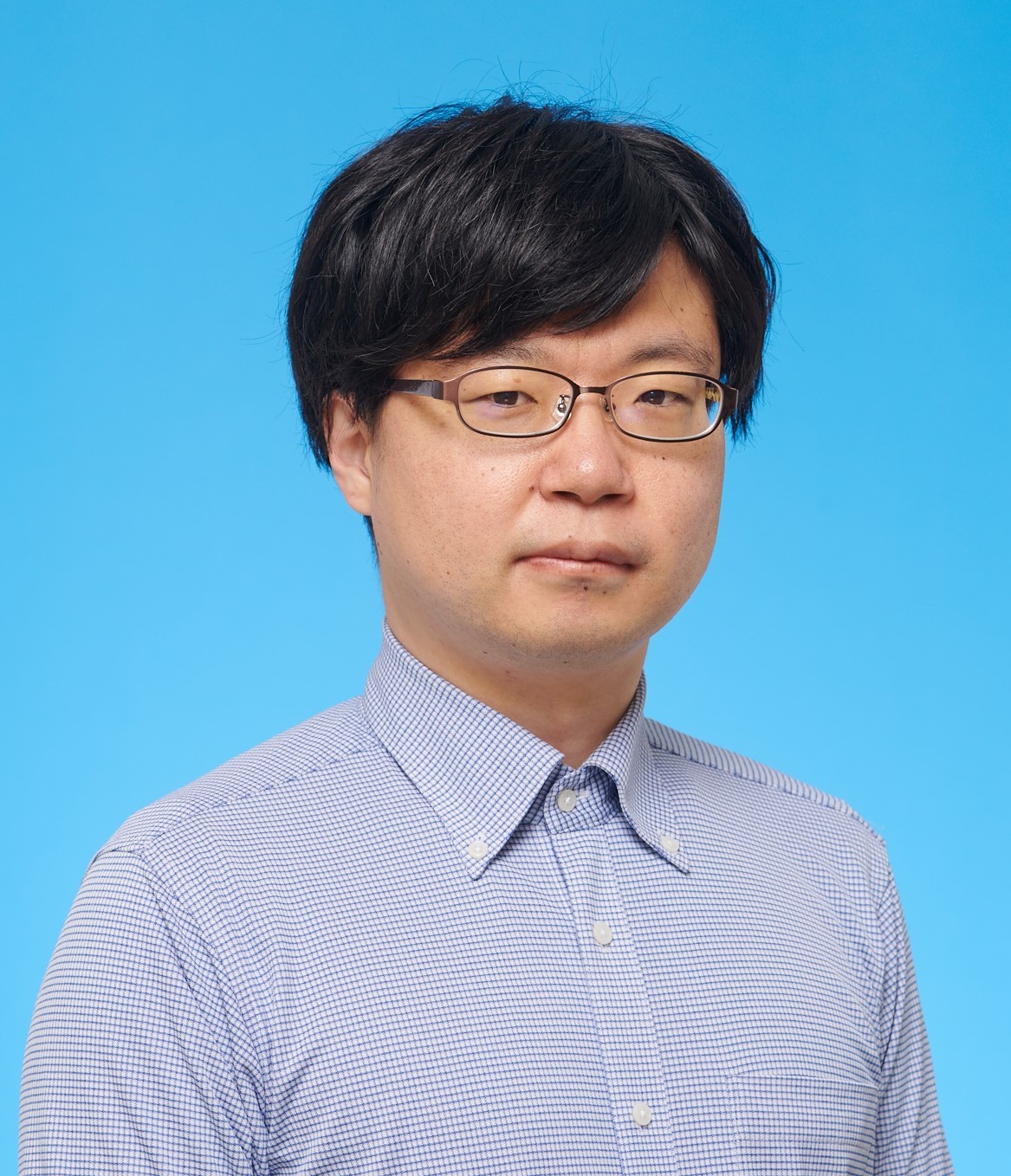
自立分散型エネルギー社会構築に向けた超小型固体酸化物形燃料電池の事業化
持ち運び可能な小型の次世代電源の実現を目指し、超小型の固体酸化物形燃料電池の開発に取り組む。セラミックス製リアクターの製造技術、内部の熱を効率よく活用する技術、燃料を機械に頼らずに送り込む技術という3つのコア技術を組み合わせ、小型かつ高性能な電源装置を作る。また、単なる試作にとどまらず、将来的な量産に向けた仕様の明確化も進める。さらに本電源を、インフラ監視用のセンサやカメラ、AI処理を行う小型端末などに搭載し、実際の使用環境を想定した動作実証を行うことで、社会実装に向けた有効性を確認する。本取り組みにより、電力供給が困難な場所における小型機器の活用可能性を大きく広げることが期待される。

新奇溶融水酸化アルカリを活用した炭素繊維強化樹脂からの高効率炭素繊維回収システム
軽量かつ強固な素材である炭素繊維強化樹脂(CFRP)は世界規模で市場が増大している一方、廃CFRPも増加している。製造におけるエネルギー負荷が大きく高価な炭素繊維を廃CFRPから高強度で回収する技術開発が望まれている。従来の方法では、回収した炭素繊維が劣化し不均一な性質であること、そのため利用用途が限られることや樹脂は利用されず廃ガスや廃液として処理されること、など課題があり普及にはいたっていなかった。本技術では、溶融水酸化アルカリ溶媒の調製技術を活用して、CFRPの樹脂のみを選択的に溶解する溶媒を開発し、高強度の炭素繊維の回収、溶解した樹脂のガス化利用、溶媒の繰り返し利用、が可能なゼロエミッションの炭素繊維回収システムの開発を目指す。
審査委員
- ・
石井 裕之
(早稲田大学 アントレプレナーシップセンター・所長、理工学術院・教授) - ・
片桐 大輔
(千葉大学大学院国際学術研究院/学術研究・イノベーション推進機構スタートアップ・ラボ・教授) - ・
金子 直哉
(神奈川県立保健福祉大学・科学技術アドバイザー) - ・
河原 三紀郎
(東京大学協創プラットフォーム開発株式会社・パートナー) - ・
後藤 優
(横浜市立大学・スタートアップ支援プロデューサー(特任教員)、共創イノベーションセンタースタートアップ推進部門・副部門長) - ・
酒井 宗寿
(茨城大学研究・産学官連携機構・准教授) - ・
白石 高志
(芝浦工業大学 SIT総合研究所・特任教授) - ・
高木 克人
(電気通信大学 産学官連携センター・特任准教授) - ・
辻本 将晴
(東京工業大学研究・産学連携本部・イノベーションデザイン機構・機構長、環境・社会理工学院・教授) - ・
中川 正樹
(東京農工大学 大学院工学研究院・特任教授) - ・
西野 由高
(筑波大学国際産学連携本部/本部審議役・教授) - ・
野嶋 卓也
(慶應義塾大学イノベーション推進本部・特任准教授) - ・
平田 光子
(東海大学学長室・次長、経営学部・教授) - ・
・
(※ 審査委員リストは五十音順にて掲載。所属は審査当時のものです。)